|
《76》 広東自由貿易試験区の可能性
広東は香港・マカオとの協力深化に重点 国務院が発表した全体計画によると、今回開設された3つの自貿区および上海の計4自貿区の面積はそれぞれ約120平方キロメートル。いずれも保税港区などを含む複数のエリアから構成され(図表1)、自貿区に投資する外資企業については、共通のネガティブリストが適用される。
このうち、広東自貿区は既存の特区である前海深港現代サービス業協力区(以下、前海)の全域と隣接する蛇口地区、また珠海横琴、広州南沙の2新区の一部による3つのエリアで構成され、珠江デルタの中心部に3つの小自貿区によるトライアングルが存在するイメージとなっている。
重点政策は原則、各エリアの従前政策を踏襲しており、前海であれば金融業や先進物流、サービス業、横琴では観光やレジャー、ヘルスケア産業、南沙では海運や金融、ハイエンド製造業などの高付加価値産業を発展させるとし、外資企業への規制緩和にもこれらを軸とする意向がうかがえる(図表2)。換言すれば、中国がこれまで香港・マカオとの間で取り組んできた経済協力協定(CEPA)の発展形であり、計画に列記された業種・分野を中心にさらなる規制緩和が図られていくこととなろう。
中国本土企業は積極的、外資企業は様子見 さて、こうした政府の方針を受け、広東省自貿区の設立前から、同区への投資に積極的な動きを見せているのが中国本土の企業である。特に、香港と隣接する前海には、すでに2万8000社を超える企業が設立登記済みで、うち9割以上が本土企業とされる。 中国本土の企業にとって前海に進出する最大のメリットは、オフショア人民元の調達にかかる規制緩和だろう。中国国内の資金調達環境は一時期に比べ改善したとはいえ、特に中小企業にとってはまだまだ厳しいのが現状だ。また、足元で中国当局は景気てこ入れのため利下げを進めているが、それでも昨年は中国本土と香港における銀行の金利差は最大で3%ポイント程度乖離した。こうした背景から、調達コストが割安な香港の金融機関からの資金調達をもくろむ本土企業の進出が相次いだと推察され、深&`市の統計によると、新規届出ベースで2013年に150億元だった香港—前海のクロスボーダー人民元ローンは2014年には同698億元へと4倍以上拡大した。 他方、外資系企業の反応は総じて芳しくない。外資系企業の場合、中国の一般地域では規制される海外からの資金借入枠が、区内に登記・設立し、実際に経営または投資を行っている企業であれば、枠を費消することなく香港の金融機関から人民元を借り入れることが可能だ。さらに香港企業の場合、人民銀行の認可があれば金利優遇措置が適用される可能性もある。また、区内企業であれば内資・外資を問わず、一部業種を対象に企業所得税の減税(25%↓15%)措置も適用されるなど、さまざまな優遇措置が図られている。 しかし、たとえば企業所得税減税は、2020年末までの限定的措置で、原則として既存法人の登記移転や支店を設立するだけでは適用対象にならない。つまり、新規に設立した現地法人しか優遇税率を享受できないため、実質的に税務メリットを享受するのは難しいということになる。こうした使い勝手の悪さが遠因となり、日系を含め外資企業の多くは、細則の公布や他社動向を見極めるというスタンスが続いている。
規制緩和の進展に期待 上海自貿区によると、同区設立から1年間に新規進出した日系企業は約100社にとどまったとされる。クロスボーダープーリングや集中決済・ネッティングなどの資金管理制度を中心に、制度改革・開放において一定の成果はあったものの、実際のビジネスに活用できている企業はごく一部にとどまり、区内に進出する企業からは、いまだ優遇政策をどうビジネスに活用できるのか不透明という声も少なくないようだ。 広東自貿区の全体計画では、前海で先行・試行されている人民元建ての各種クロスボーダースキームを広東自貿区全体に拡大していく意向がうかがえる。ただ、上海の例を見るまでもなく、せっかくの規制緩和や優遇政策も、実際のビジネスに有用でなければ、企業の活用も投資も進まない。計画にうたわれた「3〜5年の試験的な改革を通じて、国際化、市場化、法治化された事業環境を創出し、開放型経済の新たな体制を構築し、広東、香港、マカオの高度な協力を実現し、国際経済協力・競争における新たな優位性を形成」するためにも、外資企業の投資意欲を喚起する実効性のある取り組みに期待したい。 (このシリーズは月1回掲載します) 【免責事項】本稿は情報提供のみを目的としたもので、投資を勧誘するものではありません。また、本稿記載の情報に起因して発生した損害について、当行は一切責任を負いません。なお、本稿内容の一部または全部の無断複製・転載は一切禁止いたします。 |
|
|
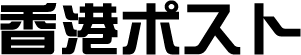


.jpg)
.jpg)