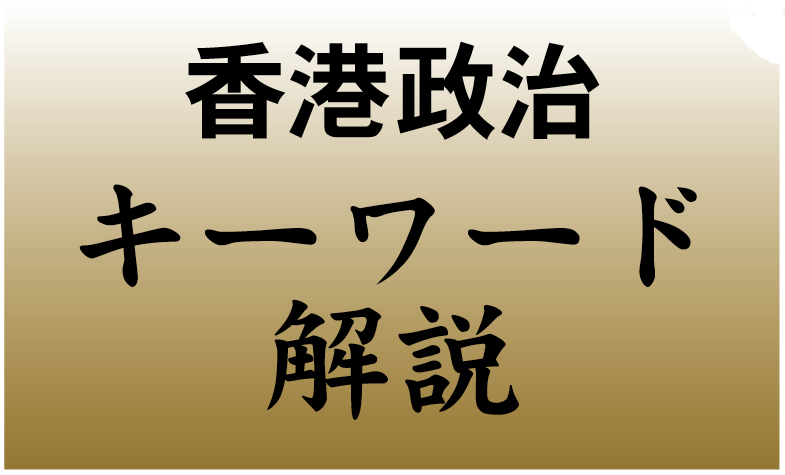
《124回》
川震十年(四川大地震十年)
香港メディアの香港政治関連の報道では、香港ならではの専門用語や、広東語を使った言い回し、社会現象を反映した流行語など、さまざまなキーワードが登場します。この連載では、毎回一つのキーワードを採り上げ、これを手掛かりに、香港政治の今を読み解きます。
(立教大学法学部政治学科教授 倉田徹)
香港市民の中国人意識
最も高まった2008年

踏みにじられた震災への善意
悲劇から十年
今回は「川震十年」をキーワードに選びました。「川震」とは、2008年5月12日に四川省汶川を震央として発生した巨大地震「四川大地震」の略称で、主に香港と台湾でこの呼び方が多く使われるようです。一方、中国本土では「汶川地震」や「5・12大地震」という呼称が広く用いられます。死者・行方不明者は、東日本大震災の4倍を超える8万人以上を数える大災害でした。
今年5月12日、この地震の発生から十年の日を迎えました。十年前、香港市民は多額の寄付で被災地を支援しました。今回、中央人民政府駐香港特区連絡弁公室(中連弁)の王志民・主任や林鄭月娥・行政長官は代表団とともに四川省を訪れ、初めての四川・香港協力会議を開きました。席上王主任は、地震発生当時、中連弁は数日のうちに届いた香港市民からの義援金の領収書3万通あまりを切るだけでも大変であったと回想しています。
しかし実際には、十年経った今振り返ると、この大悲劇は香港市民にとってもっと複雑な、苦い記憶となっているようです。
ナショナリズムのピークと減退
この大地震のあった2008年は、香港市民にとって、中国人としてのアイデンティティが最も高まった時期でした。
返還直後に発生したアジア通貨危機を受けて、香港経済は返還バブルから、急速に大不況へと落ち込んでいきました。2003年には新型肺炎SARSの流行もあって経済は最悪となり、不満を募らせた香港市民は7月1日に「50万人デモ」を起こしました。この危機を救ったのが本土の経済力でした。本土住民の香港への個人観光旅行や、香港の金融機関の人民元業務の解禁により、景気はV字回復したのです。多くの香港市民が、中央政府の「プレゼント」に感謝しました。
このような中、香港市民は自分を「香港人」よりも「中国人」とみなす意識を育てました。2008年6月の香港大学の調査では、自分は「中国人」と答えた者は38・6%と、1997年以降の調査結果で最高の数字となりました。「香港の中国人」と答えた者と合わせた広義の中国人アイデンティティを持つ者は51・9%と過半数に達し、「香港人」18・1%、「中国の香港人」29・2%と合わせた広義の香港人47・3%を上回っていました。香港市民は歴史上、中国が「国難」に直面すると、祖国を助けようとの意識を高揚させてきました。この時もまさにそうで、続いて夏に開催された北京五輪はナショナリズムのピークとなりました。
しかし、この後香港市民の中国人意識は、急速に低下していきました。本土住民・観光客の大量流入による、粉ミルクの品薄に代表される生活問題や、不動産価格暴騰による住宅難などが重要な原因として指摘されますが、「川震」に対して示された香港市民の善意が踏みにじられたことも、少なからず影響しているでしょう。香港特区政府は公費や民間からの寄付などによって100億香港ドル規模の基金を設け、復興プロジェクトを多数支援しました。しかし、これを託された四川省政府が発注した工事に多数の手抜きが見つかったり、香港の寄付で建てられた学校が、わずか1年で取り壊されて豪華なショッピング・モールに変わったりと、善意の基金が腐敗した政府によって不適切に使われたと疑われる事例が続出しました。
ナショナリズムが反中意識へと急速に転換する中で、2013年に四川省雅安で再び大規模な地震が発生し、100人を超える死者を出しました。しかし、香港赤十字への寄付は、2008年に3日間で5500万香港ドルが集まったのに対し、2013年は発生3日目までにわずか300万ドルに留まりました。当時政務長官を務めていた林鄭月娥氏は、四川省政府に1億香港ドルを渡すことを立法会に提案しましたが、民主派からは大いに反対され、市民からも批判されて支持率が低下しました。
変わらない中国への苛立ち
こうした経緯もあり、「川震十年」を前にした香港では、本土当局の腐敗を非難する論調が多数を占めました。『明報』紙では、5月9日に呂秉権浸会大学高級講師による「川震十周年の国民教育」、翌10日には評論家の陳帆川氏による「汶川地震十周年は最もよい国民教育」と題する評論が掲載されました。両者の論調は、いずれも「川震」が手抜き工事や腐敗の実態を香港市民が知る「国民教育」になったという内容で、非常に似ています。
香港大学による直近の2017年12月の調査では、「自分は中国人」と回答した者は14・5%にまで低下し、中でも18—29歳に限ればわずか0・3%でした。この十年に、香港市民、特に若者の対中感情は大きく悪化しました。しかしそれは、よく言われる、若者が中国を知らないからということではないようです。最近のある調査では、高校生の95%が本土訪問の経験があり、簡体字を読めると述べた者が85%、本土のSNS「微信」を使用している者は69%、毎月複数回本土のウェブサイトを見ると述べた者が46%と、若者の本土との接触は決して少なくないことが分かりました。調査を担当した香港教育大学の呂大楽・教授は、若者がなぜ国家への認識を持った上で国家を批判しているのかを、社会はよく理解すべきだと述べています。
2016年に主に若者の間で盛り上がった香港独立論は現実味を欠き、強い批判も浴びて減退しています。しかしながら、十年前に香港市民が見せたナショナリズムの高揚は、全く戻ってきていないと言えるでしょう。今回の「川震十年」でも、四川で取材中の香港有線電視の記者が殴打される事件が起きています。中国政府の不透明さや腐敗の体質が変わらない限り、香港市民から再び信頼を取り戻すことは容易ではないでしょう。
2015年の映画『十年』は、十年後の香港が(悪い意味で)大きく変わる未来像を描きましたが、過去を振り返っても、今の香港の姿は十年前には想像もつかないものでした。一方中国も、社会・経済はどんどん変わりますが、政治の変化はそれよりずっと緩慢に見えます。十年後の中国の政治が、良い意味で現在の姿から大きく変わることが、何よりも重要でしょう。
本連載も2008年の開始から十年を突破しました。今後ともどうぞよろしくお願いします。(このシリーズは月1回掲載します)
筆者・倉田徹
立教大学法学部政治学科教授(PhD)。東京大学大学院で博士号取得、03年5月~06年3月に外務省専門調査員として香港勤務。著書『中国返還後の香港「小さな冷戦」と一国二制度の展開』(名古屋大学出版会)が第32回サントリー学芸賞を受賞
