|
サッカー界のコロンブス ~特別企画・伊藤壇インタビュー~
これからはアジアの時代——。ビジネス界ではそう言われて久しいが、近年はJリーグが東南アジアで放送されるようになったり、クラブチームが現地のチームと提携するなど、サッカー界でもアジアへと大きく舵をきる動きが続く。アジアでプレーする日本人もここ数年で激増。そんな中、ある1つの取り組みが注目を集めている。元Jリーガーで、アジアでプレーする日本人の先駆けである伊藤壇さんが立ち上げた「チャレンジャス・アジア」だ。アジアの将来を見据える伊藤さんのさまざまな活動について話を聞いた。
前人未到!18カ国・地域でプレー
香港は私にとって5番目の移籍地です。香港リーグはアジア最古のプロリーグと聞き、いつかプレーしたいと思っていました。特に、各国代表を招いて行われていた旧正月の国際大会「カールスバーグ杯」への出場(2004年)は大きな目標でしたから、ピッチに立った時はうれしくて武者震いしたほどです。選抜メンバーのほとんどが香港で数シーズンにわたってプレーしてきた外国人選手で、移籍からわずか半年の自分が選ばれるなんて非常に光栄なことだと感じました。今でも香港のサポーターが私のフェイスブックのファンページにたくさん書きこんでくれるんですよ。香港の人はみんな温かいというか、熱いですね!
——2015年は18カ国・地域でのプレーを達成。同年は「アシックス」の広告キャラクターとしても活動し、出演した同社の公式動画『蹴劇-SHUGEKI-』も話題になりました。 アジアを舞台に闘う男たちがテーマである『蹴劇』では、私のアジアでの生活とプレーする姿を密着取材していただきました。リゾートとして有名なタイからブータンのようななかなか簡単には行けない国まで、私が住んだアジア各地の様子が分かると思います。同じように海外でプレーする日本人選手との対談やサッカー豆知識なども紹介していて、計10編という見ごたえのある内容です。
簡単に言えば、「選手のコンディションを維持する場」ですね。そのほかにいくつもの意味合いを持っています。私自身がアジアで移籍を重ねるなかで、次のチームが見つかるまでの間にたった1人で練習しなければいけない状況がよくありました。心細さを感じることもあるし、フィジカル・技術面においても練習相手がいないとコンディションやモチベーションが下がってしまいます。そこで、アジアへの移籍を望む選手同士がトレーニングしつつ情報交換できる場所があればいいなと思いました。実際に18カ国・地域でプレーした私が一緒に練習しながらアドバイスすることもできるし、日本人選手の移籍をサポートするとともに若者の就活支援にも一役買えるのではないかと考えたのです。それがこのプロジェクトを立ち上げた動機の1つです。 もう1つ、大きなきっかけになったのは、アジアのサッカーに関する問い合わせが急増したこと。移籍したいという選手からの連絡のほか、現地チームや協会との窓口になってほしいという日本のサッカー関係者からの依頼もあり、多岐にわたる需要が感じられました。誰かがその受け皿をつくらなければと考え、アジアサッカーの第一人者としてやるべきじゃないかという使命感にも駆られました。
——チャレンジャスという名称にはどのような意味が?
「Challengers」と「Challenge us」という2つの言葉に由来する造語です。「よし、行くぞ!」とか「さあ、かかってこい!」というような挑戦者として奮起する気持ちも込めています。 ——プロジェクト始動後の手ごたえはいかがですか? チャレンジャスの活動期間は毎年12月から約1カ月間、丁度サッカーの冬の移籍市場に備える時期です。気候が良くアジア各地にアクセスしやすいバンコクで、トレーニングだけでなく、練習試合、入団テストのコーディネートなども行っています。初年度の2014年は運営を手探りで進めてきましたが30選手以上集まり、手ごたえを感じました。2年目の2015年は、チャレンジャスがサポートする選手のほとんどが契約することができました。コーチ兼任として契約した選手もいて、今後はプレーヤーのみならず、監督やコーチ、フィジカルスタッフなど、指導者や専門家の移籍サポートも強化していきたいと考えています。
——最近はさまざまな支援活動にも尽力なさっています。 2004年、香港からマレーシアに移籍した直後にスマトラ島沖地震が起きて、所属チームの本拠地であるペナン島も津波被害に遭いました。被災地を訪問してさまざまなことを感じ、私に何ができるだろうかと考えるきっかけになりました。東日本大震災発生時に真っ先に頭によぎったのはそのときのことです。これまで自分がプレーしたアジアの国々に支援を呼び掛けたところ、サッカー関係者のみならず、一般の方や現地メディアまでたくさんの方が協力してくださいました。この場を借りて御礼申し上げます。 2014年に東日本大震災の復興支援事業の1つでもあるベガルタ仙台20周年記念マッチに出場した際は、被災地の子供たちとボールを蹴り、交流することができました。
今年2月は日本国政府が推進するスポーツによる国際貢献活動「Sport for Tomorrow」の一環としてネパールで行う震災復興プロジェクトに参加する機会をいただきました。Jリーグからの派遣でカトマンズ周辺の学校で子供たちにサッカーを教えたのですが、自分が2011年に選手としてプレーしていたネパールに、当時と立場は異なるものの、こうして再訪問でき大変うれしかったです。 数年前からは途上国の子供たちにボールを届ける活動「ピースボールアクション」にも協力しています。私にできることは限られていますが「サッカーで元気を届ける」、それがサッカー選手である自分にとってできる唯一の方法だと思います。私自身、いつ、どこに行っても、ボールを蹴る子供たちの笑顔にたくさんの勇気をもらっています。今後もこうした機会があれば参加していきたいです。
——講演やサッカー教室でも新しい取り組みがあるそうですが。 イベント出演やサッカー教室などはシーズンオフを利用して行っています。日本での滞在期間はそれほど長くないので、短時間でも来場者の皆さんとコミュニケーションが取りやすいトークショーをメーンにしてきました。質疑応答ではサッカーに関することから、海外でのライフスタイルまでフランクにお話ししています。実際にプレーした人間でないと分からない驚きの現地情報が飛び出したり、来場した学生さんからサッカーや部活に対する悩み相談を受けたり、講演内容は斬新かもしれませんね(笑)。 サッカー教室は地域や学校、企業などから依頼を受けて子供たちをはじめ、学校、サークルなどで指導しています。今後は、スマホなどで受講でき、動画を活用してプライベートレッスンを行う「スマートコーチ」にも参加する予定です。そして、いつか引退したら日本やアジア各地で、サッカースクールを設立したいと考えています。
——今年1月20日には初の著書『自分を開く技術』(本の雑誌社)が出版されました。 『自分を開く技術』では自分をどのようにして売り込むかということにフォーカスしました。日本の常識が通じないカルチャーギャップの中に身を置きつつ、ツワモノがうようよしているアジアでどう生き抜くか、私の体験談やアピールのノウハウを紹介しています。いわゆるサッカー本と思ってページを開くと、そうではないことに驚くかもしれません(笑)。アジア放浪のおかげで私はサッカーチームのオーナーやマネジャーは「凄腕の商売人」だということを学びました。もちろんグランドでのパフォーマンスが最重要ですが、サッカーという枠だけで物事をとらえていると、移籍も契約交渉もうまくいきません。ビジネスマンや就活生にも読んでいただけたらうれしいですね。
——伊藤さんの活躍が映画になると聞きました。今後の予定を教えてください。 40歳になりましたが、もうしばらく現役を続けるつもりです。私が次の国へチャレンジする姿を追ったドキュメンタリーフィルムをつくり、世界へ発信するという企画があります。その手始めとして撮影した予告編『FUTEN』(※参照)が2015年11月にオランダの「アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭」に出品され、広く世界から出資者や製作パートナーを募っているところです。 移籍コーディネートやアジアサッカー専門の解説者、サッカースクール設立など、各方面で「アジアとの架け橋」になることが最終的な目標ですが、今はまず自身の移籍を最優先に考え、コンディション調整中です。新たな国が決まったら、また『香港ポスト』の連載で現地の様子をご紹介します! ※編集部注:FUTENとはフーテンの意味。同予告編を手掛けた映像スタッフによると、1カ所に留まらず各地を渡り歩くけれど誰からも愛されるフーテンの寅さんと伊藤さんの姿が重なったのだとか ■伊藤壇(いとう・だん)
1975年生まれ、北海道出身。Jリーグ「ベガルタ仙台」を経て2001年から海外へ。「1年1カ国」をポリシーに、これまでプロ選手としてプレーしたのはベトナム、香港、タイ、マレーシア、ブルネイ、インド、ミャンマー、ネパール、モンゴル、ラオス、ブータンなど18カ国・地域(日本を含む)。アジアにこだわり続け、未知のリーグを目指し各地で「初上陸の日本人選手」として活躍している。最近はオフシーズンを利用し、講演、サッカークリニック、執筆活動のほか、クラブチームやプレーヤーをはじめ、企業などの「アジア戦略」に関するアドバイザリー業務も展開する。最も多くの国でプレーしたサッカー選手としてギネス世界記録申請も検討中。
|
|
|
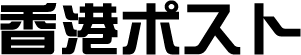


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)